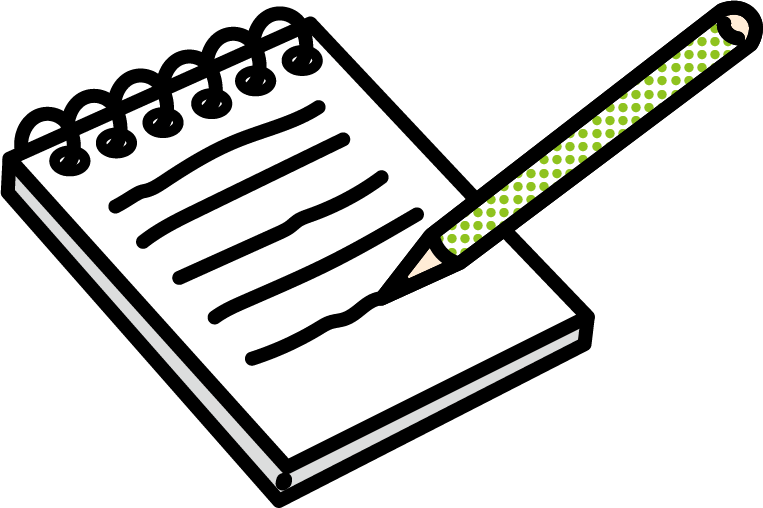数学や理科の応用問題って勉強するが大変
それでも、高得点を取るためには避けては通れない部分です。
今回は、数学や理科の応用問題について、その概要と対策について解説していきます。
発想が難しいタイプ
一つ目は発想が難しいタイプの問題です。
解法や考え方が独特で、教科書を読んでいるだけでは思いつかないような問題です。
いわゆる初見殺しというものです。
このタイプの問題は知っていれば解けるというものが多いです。
解法の流れ自体は短いケースが多いので、解き方がわかればすぐ解けるということです。
対策としては、テスト勉強の時に様々な問題に触れることです。
テストで初めて見る問題を減らすことがポイントです。
あとは、なんでそうなるのかの考え方をしっかり理解することです。
とりあえず暗記みたいな感じで勉強していると抜けていくのも早いです。
記憶を長期化するには理解することが重要です。
過程が長いタイプ
二つ目は過程が長いタイプです。
答えが出るまでに様々な要素を導いて、やっと解答にたどり着くというタイプです。
また、発想が難しいかつ過程が長いというタイプも結構あります。
このタイプの流れ的こんな感じです。
AからBが出る
BからCが出る
Cから解が出る
このように解答が出るまでにいくつかの要素を出す必要が出てきます。
Bまではたどり着いたけどそこで迷子に。
慣れないうちはそんな場合も多いです。
解答までが長いので、解き切ることが難しいです。
 塾長
塾長ミスが命取りに…
対策としては、粘り強く演習するしかないです。
基本的には上記のABCのようなチェックポイントが存在します。
それを目指して進みましょう。
最初は途中で迷子になってしまうかもしれません。
しかし、そこで諦めてはいけません。
先生の解説を聞く、解説を読み込むなどして解答までたどり着いてください。
まずは何回も解答にたどり着く経験を積んでいくこと。
そうすると自分で走りきることができるようになります。
おそらくワーキングメモリの影響が大きいタイプの問題です。
ワーキングメモリとは脳の作業領域のことです。
個人的には、脳の容量レベルが問題の容量レベルを超えると解けるようになるのではないかと。
例えば、容量レベル20の生徒がいるとします。
容量レベル10の問題は解けるけど、容量レベル30の問題は解けないみたいな感じ。
粘り強く演習するというのは、いわゆるレベル上げに近いです。
脳の容量レベルを上げることで、より高難度の問題を解けるようになるのです。
例えば、ゲームとかでボスが倒せなかったからレベル上げをするみたいな感じです。
正直なところ、私自身は脳科学などを研究したわけではないです。
今までの経験からくるイメージで話をしています。
なんとなくあっている気がしていますが、ワーキングメモリの話は参考程度にとどめてください。
まとめ
応用問題には『発想が難しいタイプ』と『過程が長いタイプ』の二つのタイプがあります。
テスト直前に詰め込む場合は、発想が難しいタイプを集中的に勉強してみましょう。
長期的に高得点を狙いたい場合は、過程が長いタイプに粘り強く取り組むことが必要になります。
脳の容量レベルをコツコツと上げていきましょう。