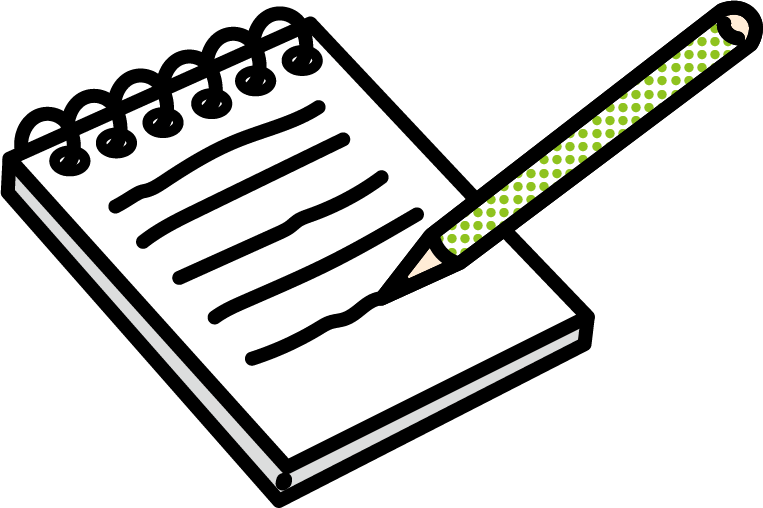数学の通知表を3から4に上げたい
そう思っている生徒はたくさんいます。
しかし、3から4というのは一つの大きな壁です。
その中で、私は何人もの生徒の数学を3から4に上げてきました。
今回は、定期テスト対策におけるポイントについて解説していきます。
基本問題の精度を上げる
精度というのは、自分が解けたと思った問題がしっかり正解になる確率です。
それを100%にします。
つまり、ケアレスミスを無くすということです。
例えば、テスト返却時に「あと10点取れた!」っていう生徒は多いですよね。
その10点が取れるだけで、3から4になる生徒が何人います。
実際のところ、ケアレスミスってミスじゃないです。
ただの演習不足です。
基本問題でミスをするレベルの勉強しかしていないということです。
基本問題だけのテストなら100点が取れる
それくらいまでやり込まないといけないです。
さらに言うと、ミスの分析もしっかりするべきです。
自分はどんなミスをするのかを意識する
ミスする問題のパターンって結構決まってます。
ミスをするパターンを予想できるまでやり込みましょう。
私個人は問題を見た瞬間に生徒がどんなミスをするのかが想像できます。
応用問題への対応
3から4を目指す場合には応用問題への対応が必須です。
しかし、注意点があります。
応用問題のすべてに対応する必要はない
教科書や問題集にある標準レベルの問題が解けるようになればいいです。
上位レベルの問題は捨てる
逆を言えば、その勇気が必要です。
目安としては80点以上が目指せるラインです。
テスト範囲を確認して、どのレベルの問題までトライするのか戦略を立てましょう。
あとは結局のところ精度の問題です。
まとめ
まずは精度を上げることが何よりも重要です。
それだけで成績は上がります。
ミスも実力のうちなので、しっかり自覚して勉強しましょう。
応用問題に関しては、徐々に得点アップを狙っていきましょう。
応用問題の勉強方法の記事も読んでいただけるとより理解できると思います。
ちなみに、4から5を目指す場合は上位レベルの問題に対応できるように勉強するだけです。
結局のところ、そこが一番難しいのです。
数学の深淵をのぞくことになります。